 もちつきのコツを知っていると、もっともちつきが楽しくなるよ。
もちつきのコツを知っていると、もっともちつきが楽しくなるよ。
これだけは知って欲しい得するコツ
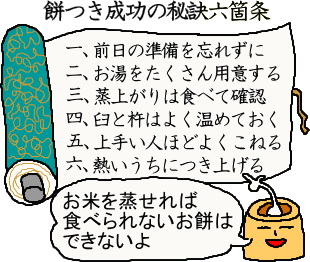
一、前日の準備を忘れずに。
前日の晩にもち米を研ぎ水に浸しておくことと、臼に水を張り、杵を水につけておくこと。簡単、これだけですので忘れずに。
二、お湯をたくさん用意する。
もちつきでは大量にお湯を使います。ポットは必需品でお湯を沸かせないときはポットにお湯を入れておきます。3~5個は用意したいところ。野外ではカセットコンロが便利です。
三、蒸上がりは食べて確認する。
蒸し上がったかどうかは食べてみて美味しいかどうかで判断します。時間はあくまでも目安。食べれば芯が残っているとか、まだ固いとかわかります。蒸すのさえ失敗しなければ食べられないお餅はできません。
四、臼と杵はよく温めておく。
もちつきの前に臼と杵をよく温めます。そうしないとおもちが冷めて硬くなってしまいます。もち米が蒸しあがる直前までお湯で温めておきましょう。
五、上手い人ほどよくこねる。
柄の付け根をしっかりと握り、体重を掛けてもち米をつぶします。こねが足りないとついたときにもち米飛び出すこともあります。慣れた人はこねてほとんどおもちにしてしまい、ちょっとついて終わりというひともいるほど。
六、熱いうちにつき上げる。
お餅は熱いうちにつき上げないと、のびないお餅になってしまいます。手早くつくほどおいしいお餅になります。子供がつくときは時間が掛かってしまうので、、大人がつき上げた後にしましょう。
その他のコツ
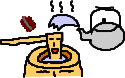
臼と杵お湯で洗うときは、杵の柄も洗ってね。
臼はお餅がつきあがったらすぐにお湯で洗います。臼の中で杵も洗います。たわしで3回ほどお湯を入れ替えて洗えばきれいになります。洗い残しが多いのは杵の柄です。柄にもお餅がついているので洗ってくださいね。
杵についた餅は木べらで取ると熱くない。
おもちがとても熱いので、熱いのが苦手な人は木べらやしゃもじを使うと楽です。
つきすぎるとおもちにコシがなくなってしまう。
粒がなくなって滑らかになったら出来上がりです。つけばつくほど柔らかいコシがないおもちになってしまいます。
臼はナナメに転がして運ぶ。
 ナナメにして臼の底の円周を地面に付けて転がして運ぶと楽で臼が傷つきません。バランスをとるのにちょっと慣れが必要かも。倒して足を挟まないように注意してください。
ナナメにして臼の底の円周を地面に付けて転がして運ぶと楽で臼が傷つきません。バランスをとるのにちょっと慣れが必要かも。倒して足を挟まないように注意してください。
お酒を飲んでのもちつきは厳禁。
アルコールを摂取してのもちつきはやめましょう。ついビールを飲みながら…なんてしてしまいますが、杵で臼を叩いたり、力の加減が上手くいかないなど、臼と杵の破損やケガにつながります。もちつきが終わってから飲んでくださいね。

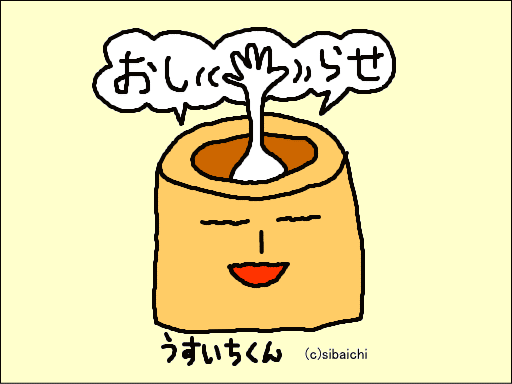

 トップページ
トップページ